
「JAMPの視線」No.298(2025年9月14日配信)
JAMP 大原啓一の視点 2025年9月14日
「JAMPのGBA誕生秘話」動画の公開
弊社・日本資産運用資産運用基盤のゴールベースアプローチに対する想いやゴールベース型資産運用ビジネス支援サービス「GBASs」の概要等について、私がお話させて頂いている動画を先週前半に弊社HPで公開しました。私は、ちょうど10年前の2015年に日本に帰国し、前職のマネックス・セゾン・バンガード投資顧問(現・マネックス・アセットマネジメント)を創業した頃から、ゴールベース型資産運用サービスの普及に全精力を傾けています。ゴールベースアプローチのサービス化・事業化に取り組んできた金融関係者は以前から多くいらっしゃいますが、そのために起業までして取り組んでいる人間は少なく(ましてや最初に経営していた会社の社長を解雇されても懲りずに再起業するような諦めの悪い人間は皆無だと思います)、日本におけるゴールベースアプローチの第一人者のひとりだと自負しています。私たちの想いや取り組みの一端をご理解いただきたく、ぜひお手すきの際にご笑覧ください。
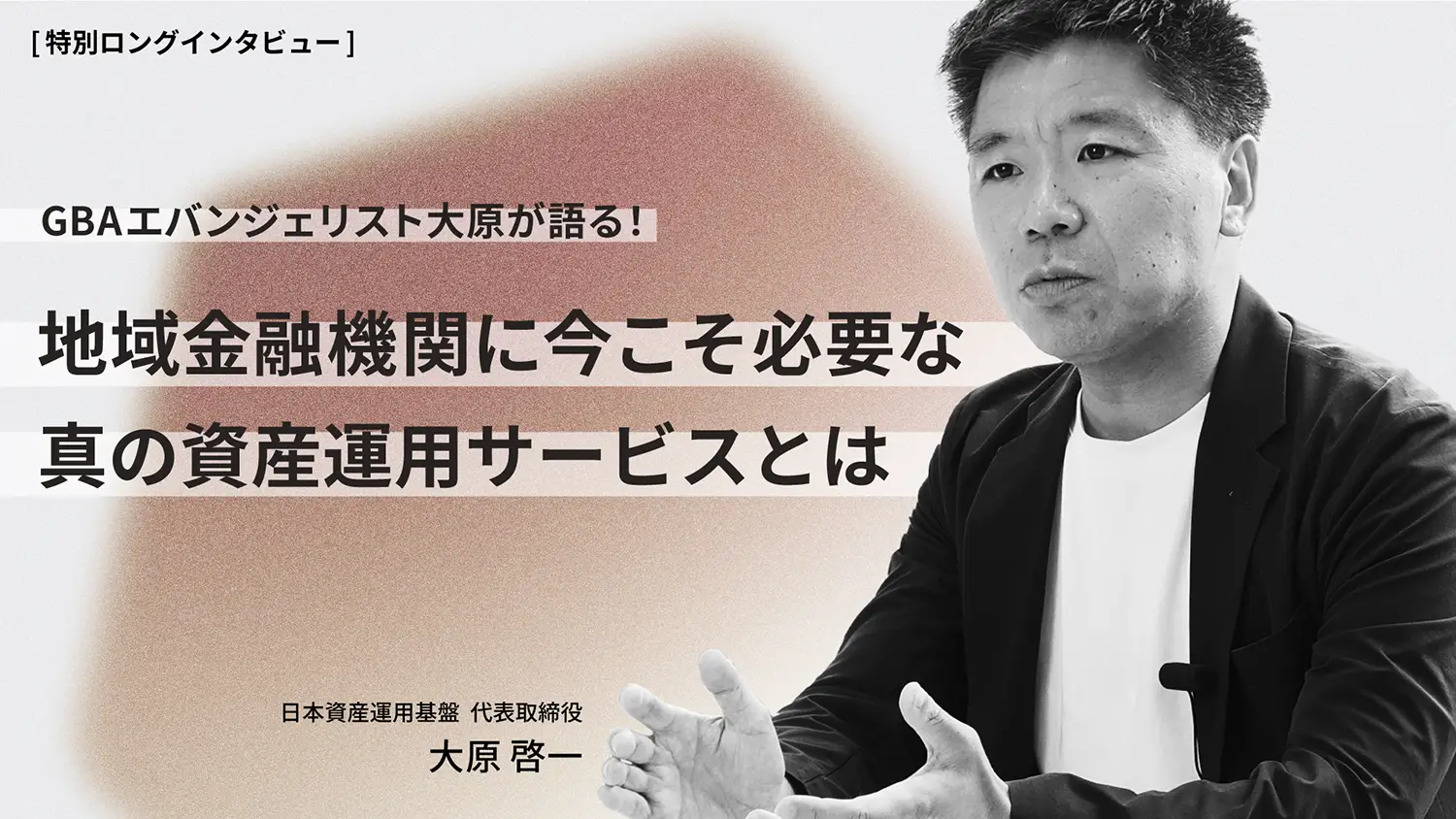
(動画)「JAMPのGBA誕生秘話」
資産運用会社の社名にみる業界の課題
さて、先週のメールマガジンで資産運用会社の社名変更についての所感を述べさせて頂きましたが、日本では社名に「アセットマネジメント」という表現を用いている資産運用会社が少なくありません。投資信託協会の正会員になっている資産運用会社は9月1日時点で233社存在しますが、そのうち「アセットマネジメント」を社名に用いている会社は3分の1強の85社にものぼります。一方、「ファンドマネジメント」を社名に用いている会社は弊社グループのJAMPファンド・マネジメントを含めて3社のみです(ちなみにJAMPファンド・マネジメント以外の2社は、日本ビルファンドマネジメントと三井不動産アコモデーションファンドマネジメントというREIT運用会社です)。
以前から私は「日本では『アセットマネジメント』と『ファンドマネジメント』が別事業として明確に区別されておらず、それゆえに資産運用会社が自ら負担の重いファンドマネジメント機能(投資信託委託機能)まで担うことが一般的であるため、本来は付加価値が大きく、生産性が高いアセットマネジメントに特化することができず、業界全体の生産性が低い水準にとどまっている」という問題意識を持っており、たびたびこのメールマガジン等でも述べさせて頂いています。
日本の資産運用会社の多くが「アセットマネジメント」を社名に用いているのも、自社の強みがまさに投資判断・投資運用業務を中心とする「アセットマネジメント」であり、そこに存在意義があるという想いを表現するというものであると理解していますが、実際にはそのほとんどが「ファンドマネジメント」、つまり投資信託委託事業を自前で営んでおり、そのために多くの専門人材や投信計理システム等の装備を備え、リソースや費用を多く投じている状況にあります。
もちろん、お客様である個人投資家や機関投資家に高品質の付加価値を提供するためには、投資信託というビークルまでも自社で責任をもって運営・管理すべきだという考えは素晴らしいものですし、私もそれを否定するつもりはありません。ただ、個々の資産運用会社の事業や業界全体の生産性を考えた場合、それぞれが自前で「ファンドマネジメント」まで対応することが適切なのだろうかという疑問を持たざるを得ません。特に、投資信託に運営・管理に携わる専門人材が業界全体でも十分に存在しておらず、その確保が中小の資産運用会社の大きな経営課題になっている状況においては、その疑問はさらに強くなります。
JAMPファンド・マネジメントが目指す業界構造改革
弊社がグループ子会社に「ファンドマネジメント」を専門とするJAMPファンド・マネジメントを設立し、ファンド・マネジメント・カンパニー(FMC/ManCo)ソリューションを提供しているのは、新しく投信ビジネスに参入を考えている資産運用会社を支援するということももちろんありますが、最終的には日本の資産運用業界を構造的に改革するという野望の実現のためです。時間はかかるかもしれませんが、大手資産運用会社を中心に運用されている既存の投資信託をすべてJAMPファンド・マネジメントのような専業のファンド・マネジメント・カンパニーに移管し、既存の資産運用会社は、その社名に込めた想いの通り、アセットマネジメント事業に専念して頂く、そんな日本の資産運用業界の姿を目指しています。
そのような業界構造の実現のためには、専業のファンド・マネジメント・カンパニーは複数存在することが必要であり、将来的にはJAMPファンド・マネジメント以外のプレイヤーも参入することが望ましいと考えています(もちろん弊社の事業成長のためには、他のプレイヤーの参入がないことがありがたいのですが)。ただ、欧州のようにファンド・マネジメント・カンパニー専業が何百社も必要かというとそうは考えておらず、せいぜい3-4社が存在していれば十分であり、それよりはアセットマネジメントに専念する資産運用会社が何百社、何千社と存在し、より高い付加価値提供に切磋琢磨するというそんな状況がベストだと考えています。
資産運用業が日本の経済成長や豊かな社会の実現をけん引するためにも、資産運用業界の生産性の向上は不可欠であると考えており、ゴールベース型資産運用サービスの普及を通じた付加価値の向上に加え、ファンド・マネジメント・カンパニーソリューションによる業界構造改革にも注力してまいりたいと思います。
JAMPメンバーの採用情報
日本資産運用基盤グループでは、事業拡大に伴い一緒に働くメンバーを募集しています。
弊社にご興味のある方、ぜひ働きたいという方はこちらからお申し込みください。
まずはお話だけでも、という方も大歓迎です!
代表の大原とのカジュアル面談でもいいかな、という方ももっとウェルカムです!!
News Picks ダイジェスト
代表取締役 大原啓一 のコメント
【無登録金融業者の調査強化 証券監視委、刑事告発可能に】
大原のコメント→
金融商品取引行為を業として行う場合には金融商品取引業登録を行う必要があり、登録業者が金融商品取引法等に違反した場合には行政処分等が行われますが、無登録業者の場合には行政処分をすっ飛ばして、いきなり刑事罰の対象となります。
SNSやコミュニティサイト等での個人による情報発信が手軽になるなか、無登録での投資助言といった金融商品取引行為も多くなっているように見受けられますが、そもそも金融商品取引業登録を行う必要があるということや、いきなり刑事罰の対象になるということがあまり知られていないように感じており、その辺りの啓発活動の必要性も感じています。
https://newspicks.com/user/121187/?ref=user_121187&sidepeek=news_15047984
【オルカン版『地球の歩き方』誕生。投資×旅行本の異色コラボ、関係者が語る出版までの舞台裏】
大原のコメント→
eMaxis Slimも独立系運用会社と同様にコミュニティ付加価値戦略を採用し、低コストだけではない付加価値によるお客様の囲い込みに動いているようであり、この戦略自体は理にかなっていると考えます。
ただ、それであれば最初からこのような付加価値提供を視野に入れ、安直に低コストに動かないで欲しかったというのが正直なところです(低コスト戦略で存在感を高めなければそもそもコミュニティ付加価値戦略も成立しないというのは重々承知していますが)。
その安直さゆえに日本の資産運用業界の健全なビジネス環境が損なわれたというダメージは取り返しがつかないものだと思います。
https://newspicks.com/user/121187/?ref=user_121187&sidepeek=news_15065662
主任研究員 長澤 敏夫 のコメント
【「投資で損をしたから人生は失敗」「売買しないと落ち着かない」専門家が警鐘を鳴らす、投資が〈目的化〉するリスク】
長澤のコメント→
投資は「手段」であって「目的」ではないというのは全く同感です。特に、ハーバード大学の研究において「「お金そのもの」を目的とする人よりも、「お金を通じて実現したいこと」を目的とする人のほうが、長期的な満足度が高いことが示されている。」というのはまさにその通りだと思います。
手前味噌ながら、弊社では、お客様の夢・希望を実現するためのゴールベース型資産運用ビジネス支援サービスを提供しておりますが、アドバイザーの方が資産運用プランのアドバイスや継続的なフォローアップを行うことで、解約率は一般の投資信託投資に比べ低くなっており、金融庁が問題視しているファンドラップにおける早期の利益確定や損切りといった顧客の行動が抑制されているのではないかと思っております。
https://newspicks.com/user/6551307/?ref=user_6551307&sidepeek=news_15030376
【やさしいニュース解説 地域金融機関の預金減少 動き始めた利用者】
長澤のコメント→
「金利ある世界」により地域金融機関の営業現場に預金獲得の要請が強まり、リテール業務において人的リソースを投資信託等の預り資産ビジネスから預金獲得にシフトしている金融機関があると聞きます。
しかし、相続による(都市部への預金)流出への対策が喫緊の課題となる中、「必ずしもそれ(=店舗を構える)だけで預金が集まる時代ではなく」、「預金金利の引き上げ」以外のさまざまなカードを持っておく必要があるというのはまさにその通りかと思います。
地域の金融機関が生き残るため、顧客との関係を強化し、金利競争に陥ることなく預金の粘着性を高めるためには、地域金融機関の強みである長年の取引を通じて熟知している顧客のライフプランを踏まえた資産運用に、将来の相続人たる家族を巻き込んだアドバイスができるかが重要になってくると思われます。
https://newspicks.com/user/6551307/?ref=user_6551307&id=6551307&sidepeek=news_15043136
インフォメーション
■メールマガジン登録
毎週日曜日22時にJAMPメールマガジン「JAMPの視線」を発信しています。
ご興味のある方は是非こちらから登録をお願い致します。
