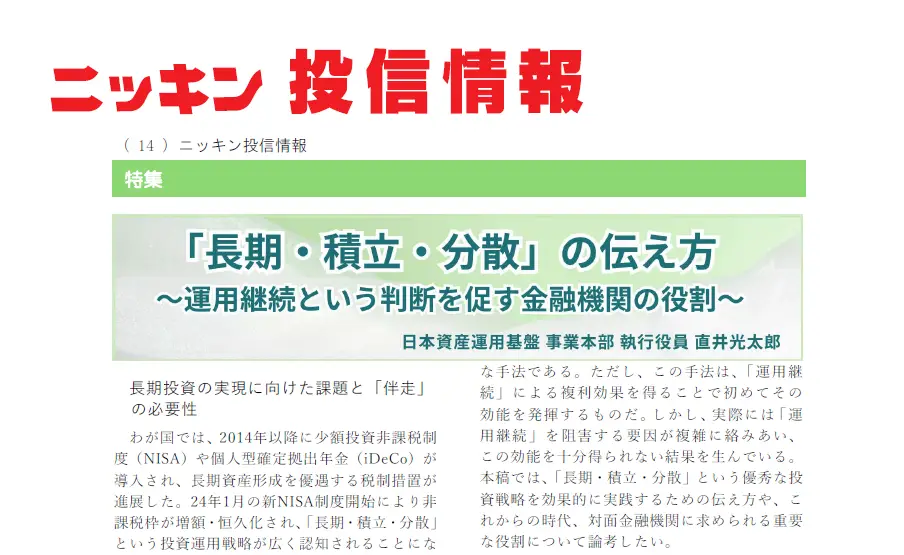「JAMPの視線」No.295(2025年8月24日配信)
JAMP 大原啓一の視点 2025年8月24日
先週頭に弊社・日本資産運用基盤株式会社及びグループ子会社の会社HPをリニューアルしました。以前の会社HPではなかなか何をやっている会社なのかということが伝わりづらく、せっかく関心を持って会社HPにアクセス頂いても、「具体的にどんなサービスをしているのか、どんな風にサポートをしてもらえるのかがわからない」というご意見を多く頂いていました。新しいHPでは提供する主要サービスの内容やそのユースケースなども丁寧に紹介させて頂いていますので、弊社取り組みをご理解頂きやすくなっているのではないかと思います。ぜひご覧ください。
日本資産運用基盤グループの新HP:https://www.jamplatform.com (アドレスは以前から変更はありません)
円建てステーブルコインの発行と証券決済への影響
さて、先週は金融スタートアップ企業であるJPYC株式会社が資金移動業者の登録を完了し、今秋にも日本初の円建てステーブルコインの発行を予定しているというニュースが金融業界を驚かせました。このニュースに続き、22日(金)には三井住友銀行や大和証券、SBI証券等の複数の大手金融機関がセキュリティトークンのセカンダリーマーケット取引におけるステーブルコインを活用したDvP(Delivery versus Payment)決済に係る実証プロジェクト(Project Trinity)を開始することが発表されたり、SBIホールディングスが株式や債券等の金融商品をセキュリティトークン化して取引する基盤を開発・提供するプロジェクトを開始することが発表されたりと、たった1週間であらゆる金融資産のデジタル化(オンチェーン化)とそれに基づく次世代取引の実現の可能性が一気に高まったように感じます。
Project Trinityに関するプレスリリースより引用
現在の証券取引は、証券保管振替機構が中央機関として株式などの金融商品と法定通貨のDvP決済が円滑に進む役割を担っていますが、例えば株式の場合には決済プロセスは日本ではT+2となっています。米国をはじめとして世界的にはT+1が広がりつつありますが、デジタル化を前提としない世界ではこの決済プロセスの短期化は容易ではないというのが金融業界関係者の共通認識だと思います。この点、金融商品と通貨がデジタル化された世界では、全ての取引がブロックチェーン上で安全に完結することになりますので、決済プロセスの短期化どころか即時決済すら実現することが不可能ではありません。日本でも不動産を中心に金融商品のデジタル化は少しずつ実現しつつあり、大阪デジタルエクスチェンジで複数のセキュリティトークンが取引されていますが、一方の通貨側のデジタル化は実現していませんでした。今回のJPYCによる円建てステーブルコインの発行は、DvP決済の前提となる通貨側のデジタル化がようやく実現するという意味で、将来的な証券取引(金融商品取引)のデジタル化とそれに基づく即時決済の実現に向けた重要な一歩であることは間違いないと思います。
資産運用業界のサービスや事業運営への影響は限定的か
それでは、この重要な一歩は私たち資産運用業界のサービスや事業運営にも大きな影響を及ぼすのでしょうか?例えば、投資信託の即時決済が実現すると、現在は投資信託の解約申し込みから解約代金の受け取りまで数営業日かかっているところ、即日で解約代金を受け取ることができれば、サービスの利便性は大きく向上することが期待されます。事業面でも、ブロックチェーン上で管理・決済が完結することで、カストディやアドミに係る費用も大きく低減することが期待できるように思います。
ただ、私は少なくとも5-10年程度の時間軸では大きな変化はないように考えています。確かに既に実現しつつあるように不動産関連商品のデジタル化を通じ、当該セキュリティトークンが個人のお客様の投資対象として存在感を高めるという意味での変化は一部にあるのでしょうが、資産運用業界のコアな領域での変化が大きくなるには相当の時間がかかるように思います。
理由①:投資信託ビークルのデジタル化の実現可能性
まず、現在の資産運用業界のサービス提供/事業運営手段として主流のビークルである投資信託のデジタル化が容易ではないと思われることです。既存のセキュリティトークンも不動産投資に係る集団投資をデジタル化はしているのですが、投資信託というビークルそのもののデジタル化とは異なります。ここに挑戦しているプレイヤーが現在存在しているのかどうかは寡聞にして知らないのですが、どのような法規制面や技術面等でのハードルがあるのか、それらを乗り越えるためのプロセスがどんなものかすらイメージができません。上述のProject Trinityにおいてもその一環としてMMFトークンの発行が予定されているとのことですが、MMFを裏付けとするトークンの発行というストラクチャーと耳にしており、そうであるならばMMFそのものをデジタル化することにはなりません。仮に投資信託に組み入れる株や債券等や決済通貨がデジタル化されたとしても、中間的に用いられる投資信託というビークルが今のままであれば、決済プロセス全体がチェーン上で行われることにはなりませんので、即時化を含むメリットは実現されないものと思われます。
理由②:資産運用サービスとして成立するための必要条件
また、こちらの方がより重要な理由かとは思いますが、資産運用サービスが投資ユニバースとする全ての金融商品がデジタル化されるのでなければ、資産運用業のサービスとして成立しないのではないかと考えます。米国のロビンフッド社が上場・非上場企業の株式やETFをトークン化し、200銘柄くらいのセキュリティトークンを対象とする取引サービスを提供しているとのことですが、全ての株式がトークン化されているわけではありません。例えば、東京証券取引所に上場する企業の一部が株式をトークン化し、それが大阪デジタルエクスチェンジで取引されたとしても、日本株を投資対象とする資産運用サービスがそれらの一部銘柄だけを取引対象とするかというとそうではないと思います。仮に決済の即時化等のメリットが実現されたとしても、あくまで資産運用サービスの付加価値の本丸はお客様への良質なパフォーマンスの提供であり、トークン化されていない企業の株式は投資対象としないということはサービスとして成立するのが困難だと思います(もちろん、現在ある不動産関連セキュリティトークンのように全く成立しないということはなく、あくまでいま存在する資産運用サービスの全てが置き換わるためにはどういう状況が必要になるのかという視点での考えです)。そうすると、投資ユニバース内の全ての金融商品、例えば東京証券取引所に上場する全ての企業の株式がトークン化されるのを待つ必要があり、そこに至るまでには相当な時間がかかるように思います。
従って、いまある資産運用業界の資産運用サービスモデルや事業モデルが今回の革新的な動きですぐに変化することは無いように個人的には考えています。ただ、いずれにせよ資産運用業界が基盤とする証券取引インフラが非連続的に革新する重要な一歩であることは間違いないと思います。上記のような私の現時点での考えが誤りであるということになるようなスピード感で業界の取り組みが進むことを期待しつつ、どのような変化が起き得るのか、そこで弊社として何ができるのか等、考え続けたいと思います。
JAMPメンバーの採用情報
日本資産運用基盤グループでは、事業拡大に伴い一緒に働くメンバーを募集しています。
弊社にご興味のある方、ぜひ働きたいという方はこちらからお申し込みください。
まずはお話だけでも、という方も大歓迎です!
代表の大原とのカジュアル面談でもいいかな、という方ももっとウェルカムです!!
News Picks ダイジェスト
代表取締役 大原啓一 のコメント
【SBIHD、地銀出資10行へ 東北銀に3%、「第4のメガ」加速】
大原のコメント→
地域銀行は地域での長年の取引を通じて構築した地元顧客との信頼関係やブランド、対面接点等、良質な戦略資産を多く有している一方、事業運営システムや金融商品・サービス、有価証券運用ノウハウ等、自前主義で対応するには非効率的な領域も多く、その意味で共通事業基盤を提供しようとするSBIホールディングスの構想に強く共感します。
ただ、その構想を実現するための手段には個人的には違和感を感じるところが少なくありません。なぜ経営権を一部保有する資本提携を前提としなければいけないのかという大きなところから始まり、具体的な施策でいうと例えば有価証券運用支援についてはSBIグループの運用商品を組み入れさせるといった利益相反的な施策を耳にしたりするところも懸念するところです。
https://newspicks.com/user/121187/?ref=user_121187&sidepeek=news_149222
主任研究員 長澤 敏夫 のコメント
【NISAの商品拡充、暗号資産の課税見直し 金融庁が要望へ】
長澤のコメント→
NISAの拡充に関する要望は、今年3回開催された「NISAに関する有識者会議」での議論を踏まえてのものかと思われます。このうち、「18歳以上となっている対象年齢の見直し」は、自分の子供や孫に早くから資産形成を始めさせたいニーズも存在するとの意見をもとに、もともとジュニアNISAがあったのでその復活に近い感じでしょうか。
また、「投資商品の入れ替えをしやすくするような制度改正」は、高齢者が、NISAで積立てた資産をよりリスクが低い商品に切り替えることができるよう、NISA口座内でのスイッチングを認めるということかと思います。「対象商品の拡充」については、「リスクが低い商品の拡充」とありますが、主に投資初心者を意識したものと思われ、一時期話題となった毎月分配型投信のことではないと思われます。この点、毎月分配型の議論がどうなったのか興味があるところです。
https://newspicks.com/user/6551307/?ref=user_6551307&sidepeek=news_14922890
インフォメーション
■メールマガジン登録
毎週日曜日22時にJAMPメールマガジン「JAMPの視線」を発信しています。
ご興味のある方は是非こちらから登録をお願い致します。