
「JAMPの視線」No.308(2025年11月23日配信)GBASsの相続機能実装
JAMP 大原啓一の視点 2025年11月23日
毎朝、出勤前にジムでジョギングや筋トレを続けているのですが、最近ついにベンチプレスで100キロを上げられるようになり、100キロ×5回のセットを定例メニューに組み込めるようになりました。バーベルを持ち上げていると、いわゆる脳内麻薬のおかげで前向きな気持ちで一日をスタートできるため、改めて筋トレにどっぷりはまっているところです。40代も後半になると身体のあちこちにガタが出始めますが、あと30年は仕事をバリバリ続けられるように今後も心身のメンテナンスに努めたいと思います。
GBASsへの相続対応機能の実装
さて、少し前になりますが、今月12日に弊社・ゴールベース型資産運用ビジネス支援サービス「GBASs」への相続対応機能の実装についてプレスリリースをさせて頂きました。この相続対応機能については、私が以前から真の資産運用サービスの完成のために必須の優先度の高い課題として掲げていたものであり、また、地域銀行や証券会社等のパートナー金融機関の皆さまからも強いご要望を頂いていたものですので、ようやく正式にご案内できるようになったことをとても嬉しく感じています。
以前から繰り返しお話させて頂いている通り、私たちは「生活を豊かにする(儲ける)ための『投資』と将来に備えるための『資産運用』は異なる」という思想のもと、一般生活者のお客様が安心・安全に将来(老後)を過ごせるような準備をお手伝いする「真の資産運用サービス」が日本中に広がることを目指しています。
現状のGBASsサービスは、将来に備えるための資産形成・運用計画を専門のアドバイザーと一緒に策定したり、継続的な伴走サポートが受けられるよう、アドバイザーが使用するコンサルティングツールの提供のみならず、裏側の仕掛けとしても「投資一任報酬内蔵型投信モデル」を活用し、細かやな積立や取崩し、リスク水準変更等ができるような工夫を凝らしています。2025年11月現在、日本中に広がるという最終的な目的地にはまだまだ遠いものの、既に約1万世帯ものご家庭の「将来に備える」をサポートさせて頂くことができており、そのサービス継続率の高さ(=解約率の低さ)を見ても、一般の投資商品とは異なるサービスとして利用して頂いていることが明らかであり、私たちの創意工夫がしっかりと機能していることに自負を持っています。
GBASsの完成に向けた問題意識
一方、現行のGBASsサービスがこのままで私たちの理想を実現するためにパーフェクトだとは考えていません。お客様と対峙するアドバイザーの皆さまへの研修や投資一任運用会社が担うポートフォリオ運用の品質管理等のソフト面でのサポートや、GBASsが実装すべきハード面の機能もまだまだこれからのところが残っていると考えています。確かに、「投資商品」ではない「資産運用サービス」をご利用頂くという目的は一定程度は満たせているものの、お客様の「将来に備える」にしっかり応えられているかというとそうではない、そんな問題意識が強くあります。そのため、今年度を迎えるに際し、私は「2025年度はGBASsの完成度を高める」と宣言し、優先的に対応すべき課題への取り組みを弊社GBASs担当メンバーに指示しました。その取り組みのひとつが今回の相続対応機能の実装だったのです。
 今年度を迎えるに際して社内で示したGBASsの完成に向けた問題意識
今年度を迎えるに際して社内で示したGBASsの完成に向けた問題意識
相続対応機能の開発・実装の背景には、ゴールベース型投資一任運用サービスの契約者と受益者が異なることによる弊害に対する問題意識がありました。つまり、私たちがご支援するお客様の将来(老後)の生活の備えというのは、投資一任運用契約の契約者その人のみを想定するものではなく、その契約者のご家族全員の将来(老後)の生活の備えであり、ご家族全員のための資産形成・運用計画を策定し、伴走させて頂くにも関わらず、契約者が死亡してしまった場合には、残されたご家族の人生は続くにも関わらず、伴走サポートがそこでストップしてしまう。それって本当にお客様の「将来に備える」ためのサービスとして十分と言えるのでしょうか。特に、日本の一般的なご家庭では、金融サービスの契約者は旦那さまであることが多い一方、長生きされるのは奥さまであることが多いように思われます。その場合、契約者である旦那さまが亡くなられても、残された奥さまの老後を引き続きサポートするような機能が必要ではないだろうか、そんなことを以前からずっと考えていました。
ただ、投資信託や株式等の金融「商品」と異なり、投資一任サービスというのは、契約者が金融機関に対して投資運用を一任(委任)するという契約関係であり、契約者が死亡しても相続の対象にならないというのが、これまでの金融業界では一般的な考え方でした。そのため、契約者が死亡すると、投資一任契約は解約となり、そこで運用されている金融商品は全てキャッシュ化され、相続人である奥さまやご家族の口座に送金されるということになります。この場合、「将来に備える」ための資産サービスの受益者であるご家族全員の利益にかなわないことが最大の問題ですが、サービスの提供側である金融機関にとっても、ストックビジネスの基礎となる投資一任契約が解約されるのみならず、お預かり資産が外部金融機関に流出するという事業面での問題が避けられません。特に、地域銀行の場合、相続人である残された家族が当該地域に住んでいないことも多く、お預かり資産が首都圏等に流出し、もう戻ってくることが見込めないという、大都市圏の証券会社以上に深刻な問題となり得ます。
相続対応機能によるお客様や金融機関にとってのメリット
私たちが新しく実装した相続対応機能では、ゴールベース型投資一任運用サービスの契約者が死亡したとしても、当該投資一任運用契約が自動的に解約となるということにはならず、あらかじめ指定された、もしくは事後的に協議で決定された相続人に投資一任運用契約をそのまま受け継いでいただくということが可能となります。ご家族がひとりいなくなってしまうという重大な変化があるため、改めて資産運用計画をアドバイザーと策定しなおす必要はあるものの、ご家族全員の安心・安全な生活のサポートというサービスを継続いただけることの安心感は、お客様にとって非常に大きいと思われます。また、金融機関にとっても、既に非常に低い水準にあるサービス解約率が更に低下することに加え、契約ごとのLTV(Life Time Value/顧客生涯価値)が向上したり、お預かり資産の外部流出を防止したりという効果も期待できます。
日本資産運用基盤は、今回の相続対応機能に加え、今後も保険機能やローン機能の実装、金融機関のアドバイザーへのGBASsメソッドの研修、投資一任運用会社のポートフォリオの品質管理等、お客様の「将来に備える」をより高次元で実現できるよう、GBASsサービスのブラッシュアップに努めてまいります。
以下、余談です
日本資産運用基盤のGBASsサービスはもともと創業者である私の構想からスタートし、「投資一任運用報酬内蔵型モデル」の開発等、サービス設計や機能開発等はこれまで私が主導する形で進めてまいりました。ただ、ここ2年ほどは金融・資産運用業界内外から弊社の理念に賛同する多くのメンバーが参画してきてくれており、足もとのサービス運営やパートナー金融機関との連携は、私の手を離れ、GBASsチームメンバーが組織的に進めるという安定した体制になっていることをとても嬉しく、誇らしく感じています。
 GBASsの営業推進やサービス運営・機能開発を担う2名の担当役員 今回の相続対応機能についても、GBASs企画チームのチームリーダーの関とチームメンバーの山口の2名が、弁護士事務所や金融庁との折衝、ストラクチャー検討、システム面・業務面での課題整理等、開発・実装を主導してくれました。関はもともと私が20代から30代半ばまで働いていた日系資産運用会社での先輩であり、資産運用業務やシステム企画等に長けた人間ですが、山口は今年春に入社するまでは金融業界未経験であったものの、その法律知識を武器に今回のプロジェクトの成功に大きく貢献してくれました。
GBASsの営業推進やサービス運営・機能開発を担う2名の担当役員 今回の相続対応機能についても、GBASs企画チームのチームリーダーの関とチームメンバーの山口の2名が、弁護士事務所や金融庁との折衝、ストラクチャー検討、システム面・業務面での課題整理等、開発・実装を主導してくれました。関はもともと私が20代から30代半ばまで働いていた日系資産運用会社での先輩であり、資産運用業務やシステム企画等に長けた人間ですが、山口は今年春に入社するまでは金融業界未経験であったものの、その法律知識を武器に今回のプロジェクトの成功に大きく貢献してくれました。
GBASsサービスはこのような素晴らしいメンバーで組織的にしっかりと運営され、ブラッシュアップされているのだということを手前味噌的に自慢させて頂きつつ、これからの更なる推進に向けて、金融・資産運用業界内外からの新たなメンバーの参画を募りたく、余談までにアピールさせて頂きます。ご関心あるかたは是非とも大原までご連絡ください!
GBASs企画チームリーダー・関の社員インタビューページ:https://www.jamplatform.com/recruit/voice/6
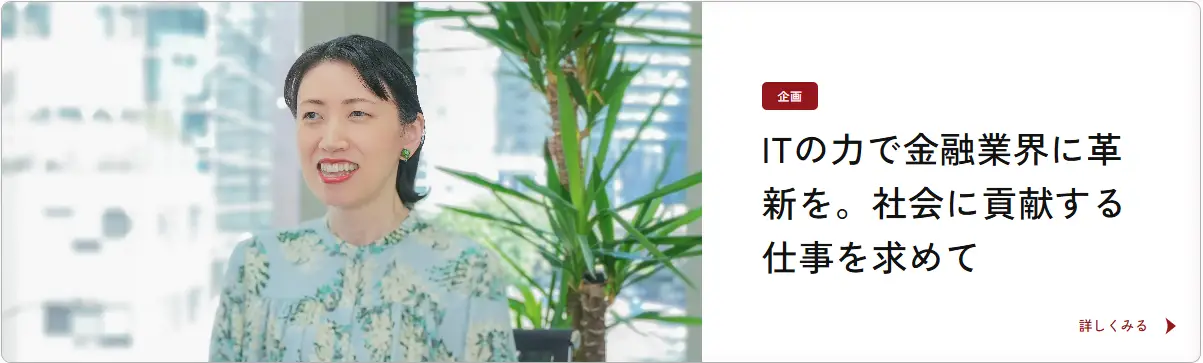
GBASs企画チーム所属・山口の社員インタビューページ:https://www.jamplatform.com/recruit/voice/3

JAMPメンバーの採用情報
日本資産運用基盤グループでは、事業拡大に伴い一緒に働くメンバーを募集しています。
弊社にご興味のある方、ぜひ働きたいという方はこちらからお申し込みください。
まずはお話だけでも、という方も大歓迎です!
代表の大原とのカジュアル面談でもいいかな、という方ももっとウェルカムです!!
News Picks ダイジェスト
代表取締役 大原啓一 のコメント
【自民党の資産運用立国議連、「つみたて投資枠」年齢制限撤廃 高市首相に提言】
大原のコメント→
政権が新しくなっても「資産運用立国」の旗印が引き続き掲げられていることに心強さを感じます。資産運用ビジネスの高度化・活性化に対して理解がある政治家が増えることは金融・資産運用業界にとっても有益なことですので、この流れが継続することを期待しますし、業界の内側にいる私たちからも理解を深めて頂くための色々な働きかけをしなければならないということを改めて思いました。
https://newspicks.com/user/121187/?ref=user_121187&sidepeek=news_15534617
主任研究員 長澤 敏夫 のコメント
【日本生命がスパイ活動の組織的指示をひた隠し】
長澤のコメント→
内部情報の持ち出しもさることながら、会議資料には「あくまでも銀行員として募集を行うため、FDの観点からも本社商品を過度に販売することの行内での見え方にはご留意ください」とあり、「本社商品を過度に販売しないよう」ではなく、「本社商品を過度に販売することの行内での見え方に留意」と、過度に販売することが前提となっているのには驚きました。
FD(顧客本位の業務運営)は当初プリンシプルベースから始まり、足元一部ルール化されました。個人的にはルール化は必要ないのではないかと思っていましたが、やはり仕方がないのかもしれません。
https://newspicks.com/user/6551307/?ref=user_6551307&sidepeek=news_15508726
インフォメーション
■メールマガジン登録
毎週日曜日22時にJAMPメールマガジン「JAMPの視線」を発信しています。
ご興味のある方は是非こちらから登録をお願い致します。
