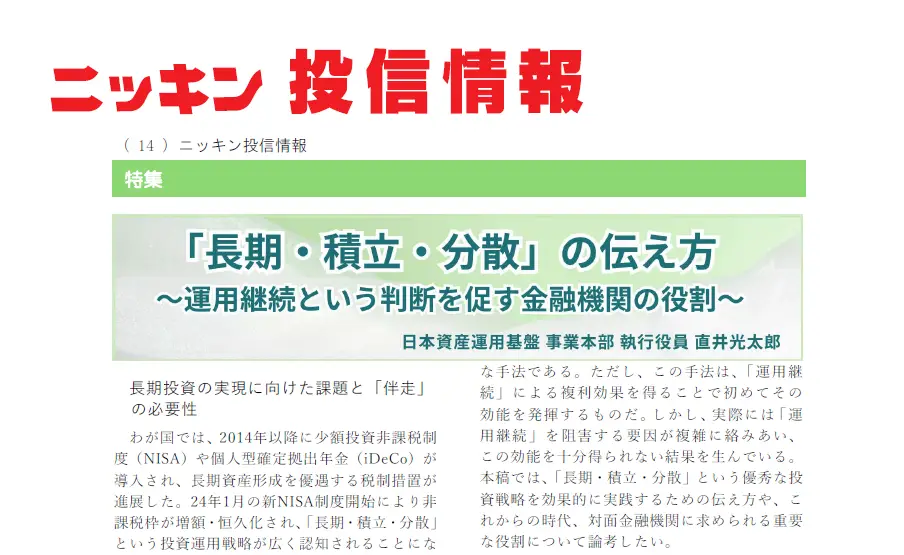「JAMPの視線」No.302(2025年10月12日配信)
JAMP 大原啓一の視点 2025年10月12日
先週頭に年に1回の人間ドックを受診したのですが、せっかくのタイミングなので人間ドックをはさんで1週間ほど禁酒をしてみました。普段は(割とがっつりと)お酒で心身の消毒に励む毎日を過ごしているため、禁酒して数日経つと、手が震えたり、変な汗をかいたりという軽いアルコール離脱症状が出て、我ながらびっくりしました。年齢も年齢ですので、これからは週に1-2日ほどの休肝日をもうけなきゃなと改めて感じました。ちなみに人間ドックの結果は肝臓の数値も含めて健康優良児であるというものでしたので、ご安心ください。
コモンズ投信様の新しい公募投信事業をお手伝い
さて、先週木曜日にプレスリリースを出させて頂きましたが、弊社は、日本版ファンドマネジメントカンパニー機能を活用した投信ホワイトレーベルサービスの提供を通じ、独立系資産運用会社であるコモンズ投信様の新しいアクティブ運用公募投信事業のお手伝いをさせて頂くことになりました。コモンズ投信様といえば、一般の生活者に対してのみならず、高度な投資運用・リスク管理等を要求する機関投資家に対しても資産運用サービスを提供する等、知見や技術、豊富な実績を有する日本を代表する独立系資産運用会社の1社であり、そのようなエスタブリッシュドな資産運用会社の新規事業をお手伝いさせて頂けることを光栄に感じています。
今回の案件は、パートナーとなる資産運用会社の公募投信事業のお手伝いをさせて頂くという点がまず弊社にとって新しい取り組みになります。弊社がお手伝いするのは、コモンズ投信様がお客様向けに設定・提供する公募投信の裏側でマスターファンドとなる私募投信を設定し、コモンズ投信様と共同運用する部分のみではありますが、最終的に一般の生活者のお客様の資産運用をお手伝いする公募投信の事業をお手伝いさせて頂けることはとても嬉しく感じています。プレスリリースでコモンズ投信の伊井社長も仰って下さっていますが、公募投信のみならず、将来の機関投資家向け私募投信への拡張もスムーズにできるよう、ストラクチャリングの提案をさせて頂いたことを含め、弊社ならではの付加価値をご提供できたように感じています。
コモンズ投信様の事業構想を実現するストラクチャーを提案させて頂きました
意義 - 業界の生産性向上に向けた第1歩
また、そうした点以上に今回の案件が特別なのは、既に投資信託委託業のライセンスや必要な投信計理システム等の装備を自前で備えているコモンズ投信様が、自社単独で新しい公募投信を設定・運用するのではなく、敢えて弊社の投信ホワイトレーベルを利用されたという点にあると考えています。弊社の投信ホワイトレーベルのこれまでの実績は、公表されている九州みらいインベストメンツ様やあすかコーポレイトアドバイザリー様の案件のように、自社では投資信託委託業のライセンスや必要な装備を備えていないなか、負担少なく投信ビジネス参入するために弊社サービスをご利用頂いているケースが中心です。この点、今回のコモンズ投信様の案件は、自社単独でも対応可能ではあるものの、バックオフィス業務等の負担を軽減し、より付加価値の高い投資運用業務やお客様とのコミュニケーション等に集中するために、敢えて投信ホワイトレーベルサービスを利用されたというところがこれまでのご支援案件とは異なって新しいところです。
日本の資産運用業界の生産性向上には「投資信託委託」業務の分離が必要
これまでも繰り返し発信させて頂いている通り、弊社は、日本の資産運用業界の効率性・生産性向上のためには、「アセットマネジメント」と「ファンドマネジメント」の分離が必要であり、資産運用会社は高付加価値の「アセットマネジメント」業務に集中し、「ファンドマネジメント」業務は外部の専業ファンドマネジメントカンパニーに任せるような役割分担が業界全体に広がることが重要であると考えています。そのためには、新しく投信ビジネスに参入する資産運用会社がこの役割分担を前提とした事業モデルを構築するだけではなく、既に投信ビジネスを営んでいる資産運用会社においても、新規設定の投資信託で外部の専業ファンドマネジメントカンパニーの投信ホワイトレーベルサービスを利用したり、既存の投資信託を委託者変更の形で事業モデルを変更する等の動きが必要となります。その意味で、今回のコモンズ投信様による投信ホワイトレーベルサービスの利用という事例は、単にひとつの新規設定の投信に係る取り組みということに留まらず、日本の資産運用業界があるべき方向に進むための貴重な第1歩であると私は考えます。
10月7日のNikkei Financialで弊社ETFホワイトレーベルをご紹介頂きました
先週前半のNikkei Financialで弊社のETFホワイトレーベルサービスの取り組みが取り上げられましたが、ETF事業への参入においては、自社で投信委託業のライセンスや必要な装備を備えている日系大手運用会社もETFホワイトレーベルの利用を検討して下さっています。きっかけとなるユースケースは多様かもしれませんが、そのように既存の資産運用会社において少しずつ「アセットマネジメント」と「ファンドマネジメント」の分離が実績として積み重なり、効率性・生産性が高い資産運用業界へと着実に向かうことを期待したいと思います。
JAMPメンバーの採用情報
日本資産運用基盤グループでは、事業拡大に伴い一緒に働くメンバーを募集しています。
弊社にご興味のある方、ぜひ働きたいという方はこちらからお申し込みください。
まずはお話だけでも、という方も大歓迎です!
代表の大原とのカジュアル面談でもいいかな、という方ももっとウェルカムです!!
News Picks ダイジェスト
代表取締役 大原啓一 のコメント
【欧米に周回遅れの東証ETF、黒子に託す資金集め: NIKKEI Financial】
大原のコメント→
日本資産運用基盤グループの子会社であるJAMPファンド・マネジメントが提供する日本版ファンドマネジメントカンパニーソリューションは、アセットマネジメントとファンドマネジメントの分離を通じ、資産運用会社に高付加価値のアセットマネジメント業務に集中頂くためのインフラソリューションです。
東京証券取引所が目指す日本のETFマーケットの活性化においてもこのインフラソリューションを用いたETFホワイトレーベルの仕組みはカギになることが期待されており、同証券取引所が進めるアクティブETFの上場基準の緩和と平仄を合わせる形で、ETFホワイトレーベルの利用の促進に取り組んでまいりたいと考えています。
記事でもご紹介頂いている通り、日本の資産運用会社に加え、足もとは米国・英国・シンガポール・台湾・オーストラリア・インド・香港等の資産運用会社からも弊社の日本版ファンドマネジメントカンパニーソリューションを用いた日本籍ETFの組成・上場の相談を頂いており、来春には複数のETFのローンチを目指しています。
(記事より引用)
国内で新たにETFの企画・運営を始める際には国内法上の届け出や申請、体制整備が必要だ。日本資産運用基盤は傘下のJAMPファンド・マネジメント(東京・千代田)が必要な事務を一手に引き受ける。いわば、事務と運用の分業だ。同社には米英など7カ国・地域から問い合わせが寄せられており、年度内に複数件の上場が実現する見通しだ。
(引用終わり)
https://newspicks.com/user/121187/?id=121187&ref=user_121187&sidepeek=news_15214785
【三井住友銀行、顧客のリスク許容度を改定 - 日本経済新聞】
大原のコメント→
金融機関がお客様に投資信託等のリスク性金融商品を提案する際、お客様のリスク許容度を診断したうえで金融商品を提案することが一般的ですが、そもそもこのリスク許容度についての誤解が少なくないように感じています。
リスク許容度というのはまさにその表現の通りでそのお客様が取得(許容)できるリスクの上限を意味しており、最適なリスク水準とは異なります。最適なリスク水準はリスク許容度を上限としてそれよりも下の水準のどこかにあるものであり、お客様の利用目的や状況等をヒアリングしながら、探る必要があります。
ただ、ゴールベースアプローチの考えが定着していない金融機関の現場においては、この最適なリスク水準を探るというプロセスが行われず、というか正確には将来のゴールから現在のアクションを逆算するという発想がないため、そのようなプロセスがあることも想定されず、リスク許容度=最適なリスク水準という前提で提案がされてしまっていることが多いように感じています(ロボアドバイザーサービスの多くも、「あなたのリスク許容度は●なので、●のポートフォリオが最適です!」のように同じ誤解に基づいて設計されてしまっているように思います)。
https://newspicks.com/user/121187/?ref=user_121187&sidepeek=news_15241958
主任研究員 長澤 敏夫 のコメント
【三井住友銀行、顧客のリスク許容度を改定 - 日本経済新聞】
長澤のコメント→
リスク許容度について何段階で把握するのが正解かはわかりませんが、把握したリスク許容度ランク以下の商品しか提案してはいけないとするのがコンプライアンス上、一般的かと思います。しかしながら、顧客のポートフォリオ全体で見て一定の許容度に収まるのであれば一部リスクの高い商品を提案しても構わないとする考え方もあろうかと思います。また、手数料が高くなるからか、リスク許容度いっぱいの商品を提案することが多いのですが、ゴールベースの考え方に基づくのであれば、ゴールが達成できる範囲でのリスクテイクに留めるのが顧客本位かと思われます。
https://newspicks.com/user/6551307/?ref=user_6551307&sidepeek=news_15241958
インフォメーション
■メールマガジン登録
毎週日曜日22時にJAMPメールマガジン「JAMPの視線」を発信しています。
ご興味のある方は是非こちらから登録をお願い致します。