
「JAMPの視線」No.293(2025年8月10日配信)
JAMP 大原啓一の視点 2025年8月10日
今日から家族が妻の実家の滋賀県・長浜に帰省しており、1週間ほどのひとり暮らしが始まります(とはいえ、カレンダー通りに働く予定ですので、ひとりで気ままに過ごすのは今日と明日の1日半ほどですが)。小学校5年生の長男は学校や塾の宿題をてんこ盛りに持って帰っているため、同年代の親戚たちと遊び倒すということはなかなか難しいかもしれませんが、東京の日常から離れた夏休みを楽しんでもらいたいと思います。
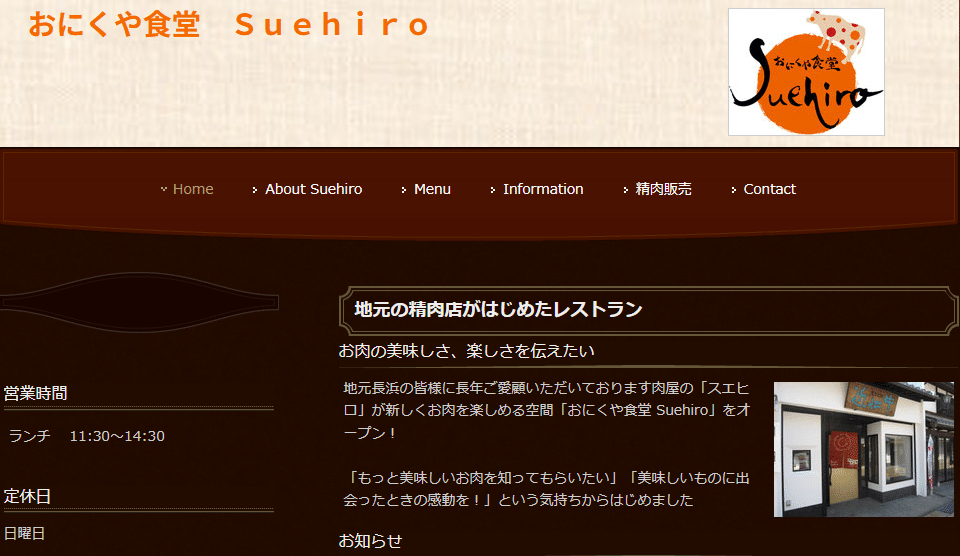
さて、フィッシング詐欺などによる証券口座への不正アクセス・取引被害が拡大していることを受け、証券会社が生体認証などフィッシングに耐性のある多要素認証の実装をするよう、金融庁が監督指針を改正しました。また、証券会社のみならず、金融サービスを提供するその他の金融業態に対しても、不正アクセス対策の強化を求めるとともに、安全性が確保できないサービスは停止の検討を促すということが報じられています。
今回の一連に動きに対しては、不正アクセスの被害を受けた大手証券会社の補償の内容や程度等に主に注目が集まっていきたように思いますが、個人的には今後の対策強化の負担増大による中小規模の金融機関への影響が大きくなることを懸念しています。例えば、地銀系証券会社や独立系証券会社は、今回の一連の不正アクセスの被害を被っていないところが多いように見受けられますが、そのほとんどが対面取引のみならず、インターネット取引を顧客に許容しており、生体認証を含む多要素認証の実装をこれから新しく行うとなった場合、費用面の負担は非常に重いと思われます。株式売買委託等手数料や投信販売手数料の無料化、投信の信託報酬の低下傾向等を受け、中小規模の証券会社の従来型事業モデルの持続可能性はこれまでも懸念されるところですが、今回の流れはこのような懸念に拍車をかけるものだと考えます。地域証券会社においては、顧客接点での付加価値提供に特化するため、証券会社ライセンスを返上し、大手証券会社に所属する金融商品仲介業者に事業転換するところが増えていますが、その動きがこれからさらに加速することが予想されます。
また、証券会社や銀行等と同程度の厳格な対応が求められるかどうかは不明ですが、自社が運用する投資信託の販売会社も兼ねている投信直販会社への影響も懸念されます。以前から繰り返し申し上げている通り、投信直販という事業モデルがもはや限界を迎えているのは明らかですが、これまで対応していない生体認証などの実装が必須とされた場合、投信直販に外販を組み合わせるというソフトランディングではなく、投信直販をギブアップし、外部の販売金融機関に直販事業を移管し、全面的に外販モデルに切り替えるというようなハードランディングを余儀なくされることすらも予想されます。 不正アクセスによる被害という不幸な事案とその対応強化が証券・資産運用業界の事業モデル転換にどのような影響を及ぼすのか、引き続き注意して見守りたいと思います。
News Picks ダイジェスト(代表取締役 大原啓一)
【人気のオプション戦略をETFに、東証が制度変更検討-金融庁と交渉】大原のコメント→
今年春のアクティブETFの上場基準の緩和に続き、東京証券取引所のアクティETF市場の活性化に取り組む姿勢は足もととても積極的&柔軟な印象です。
欧米に比べて日本のETF市場の存在感はまだ発展途上であり、弊社も6月上旬に東京証券取引所と連携して発表させて頂いたETFホワイトレーベルサービスの提供を通じ、ETF市場の活性化に貢献してまいりたいと思います。
News Picks ダイジェスト(主任研究員 長澤敏夫)
【中堅の外資生保、乗合代理店からの要求に苦慮 変額保険手数料で】
長澤のコメント→
銀行等の金融機関代理店では、金融庁の指導もあり9年ほど前から生命保険会社から受け取る販売手数料率を顧客宛に自主的に開示するようになっていますが、記事にあるような乗合代理店ではおそらく開示はしていないのでしょう。販売手数料もその原資は顧客の払う保険料であり、高い手数料は顧客の運用成果に影響するのが一般的です。このように、顧客と代理店の間には利益相反の可能性が存在しています。こうした中、利益相反の可能性と手数料等についての情報提供がルール化(金融商品取引業等に関する内閣府令の改正。12月施行)され、例えば仕組み債や投資信託を販売したり仲介したりする事業者は販売手数料の開示が求められるようになりましたが、運用タイプの特定保険契約は対象にはなっていません。販売主体や商品により求められる開示に差があり、イコールフッティングになっていないように思われます。
